国民年金について
国民年金のしくみ
国民年金には、日本に住む20歳から60歳になるまでのすべてのかたが加入対象になります
国民年金は、すべてのかたの生涯にわたって生活の維持、向上を図るため老齢・障害・死亡などに関し給付を行う制度です。
自営業や農林漁業のかた、学生のかたも、厚生年金や共済組合に加入しているかたや、その配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。
国民年金に加入しなければならないかた
・第1号被保険者……自営業や農林漁業、学生、フリーターなど
・第2号被保険者……会社員や公務員など
・第3号被保険者……第2号被保険者に扶養されている配偶者
20歳になり国民年金に加入されるかたへ
国民年金は20歳の誕生日の前日から加入することになります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金に希望で加入できるかた(任意加入)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
1.年金額を増やしたいかたは65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人のかたも任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
国民年金の届け出
就職したときや退職したときには、種別が変わりますので、届出が必要です。
| 会社を退職して、自営業を始めたとき、 または次の職を探しているとき |
第2号被保険者→第1号被保険者 |
役場 |
| 会社を退職して、会社員である配偶者の扶養に入ったとき |
第2号被保険者→第3号被保険者 |
配偶者の 勤務する会社 |
| 会社員である配偶者の扶養に入っていたが、扶養からはずれたとき |
第3号被保険者→第1号被保険者 |
役場 |
国民年金の保険料
第1号被保険者の保険料
・定額保険料 月額17,510円 (令和7年度) 年度により金額に変更があります。
・付加保険料 月額400円(付加保険料納付は任意ですので申請が必要です。)
付加保険料のみの納付は出来ません。定額保険料+付加保険料の金額となります。
付加保険料を定額保険料に加算して納付されたかたは、将来年金受給開始時に【200円×付加保険料納付月数】の付加年金が加算されます。つまり2年間で支払った付加保険料の全額を受給することになります。ただし、この付加年金には物価スライドの適用はありません。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
年金給付の種類
国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付として次の3種類の基礎年金があります。また第1号被保険者を対象とした独自の給付があります。
1.基礎年金
国民年金の独自給付(第1号被保険者が対象)
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
| 年金の種類 | 請求窓口 | |
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者期間のみの場合 | 役場 |
| 第3号被保険者期間を含む場合 | 年金事務所 | |
| 障害基礎基礎年金 | 初診日が第1号被保険者期間中や20歳前にある方 | 役場 |
| 初診日が第3号被保険者期間中にある方 | 年金事務所 | |
| 遺族基礎年金 | 死亡日が第1号被保険者期間中にある方 | 役場 |
| 死亡日が第3号被保険者期間中にある方 | 年金事務所 | |
| 寡婦年金等 | 寡婦年金、死亡一時金 | 役場 |
| 請求に必要な書類等 | ||
| 年金手帳、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄本、この他に必要な書類がある場合もあります。 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
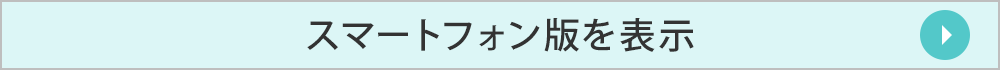








更新日:2025年06月30日